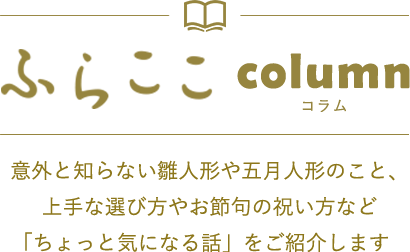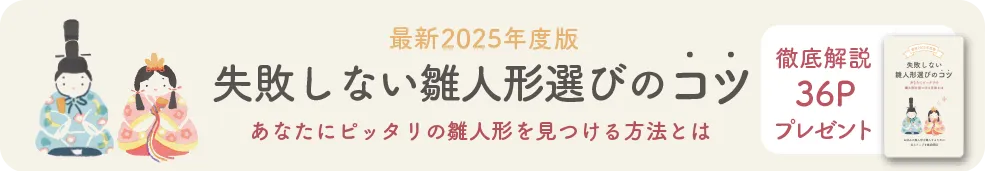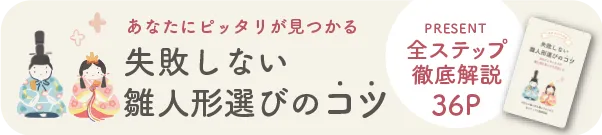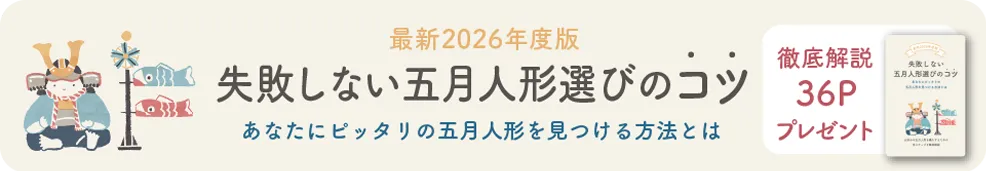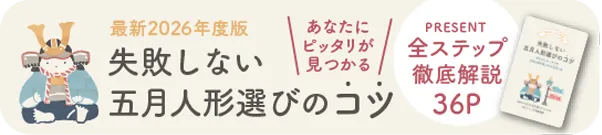3月3日の桃の節句には雛人形を飾ってお祝いするケースが一般的ですが、さらに華やかな雰囲気を楽しみたい場合には「雛祭りらしい食べ物」を用意されてみてはいかがでしょうか。古くから縁起担ぎとして多く食べられている行事食があり、食卓に並べるとより一層スペシャルな雛祭りをお楽しみいただけます。
そこで、今回は雛祭りの代表的な食べ物を7つピックアップし、それぞれの特徴や意味合い、作り方をご紹介します。ぜひ参考にしながら、雛祭りの日ならではの色彩豊かな食卓をお楽しみください。
\ つるし飾りでお祝いを素敵に演出✨ /
雛祭りの代表的な食べ物7選
それでは早速、雛祭りの代表的な食べ物をチェックしていきましょう。
今回は次の7つの食べ物をご紹介します。
1.白酒・甘酒
2.菱餅
3.ひなあられ
4.桜餅
5.ちらし寿司
6.手まり寿司
7.はまぐりのお吸い物
以下でご紹介する由来や意味合い、作り方を参考に、ぜひご家庭オリジナルの雛祭りメニューを考えてみてください。
1.白酒・甘酒
雛祭りの飲み物といえば、白酒や甘酒です。もともとは桃の花を酒に浸した「桃花酒(とうかしゅ)」を飲む風習がありましたが、江戸時代頃からは桃の花との対比が美しい「白酒」が好まれるようになっていきました。
とはいえ白酒にはアルコールが含まれているため、お子さま向けには「甘酒」がおすすめです。ちなみに酒粕を用いて作られるタイプはアルコールを含むため、ごはんに米麹を混ぜて作られるノンアルコールのタイプを用意しましょう。
|
●甘酒のレシピ ※米麹を用いる場合
【材料】
【作り方】 |
2.菱餅(ひしもち)
菱餅も、雛祭りにおける伝統的な行事食のひとつ。蓬(よもぎ)を入れた緑、菱の実(ひしのみ)を入れた白、そしてくちなしを入れた桃色の3色が重なったひし形のお餅です。
この3色の意味にはいくつかの説があるため、ここでは一般的に多く取り上げられることの多い2つの説をご紹介します。
〇それぞれの色から自然が連想され、菱餅を食べることで自然のエネルギーを取り込めるという意味合い
緑:木々の芽吹き(植物のエネルギー)
白:雪の大地(大地のエネルギー)
赤(桃色):血・生命(生命のエネルギー)
〇それぞれの色に込められた願いや祈りとしての意味合い
緑:健康や長寿
白:清浄
赤(桃色):魔除け
上記のように細かな意味合いとしては諸説ありますが、女の子の健やかな成長や子孫繁栄への願いが表現されている点は共通しています。何よりもカラフルで華やかさを演出できるため、ぜひ菱餅を雛飾りや食卓などに取り入れてみてはいかがでしょうか。
|
●菱餅のレシピ(約15個分) 【材料】 【作り方】 ②炊けたもち米と少量の砂糖を耐熱性のボウルに入れ、めん棒やすりこぎなどですりつぶします。 ③10分程度行ってある程度粒感がなくなってきたら、緑・白・赤の3色の分量に取り分けます。赤用には食紅を、緑用にはよもぎ(または青のり)を混ぜながらまとめます。 ④3色それぞれをラップで包み、めん棒などで平らに伸ばします。そしてまな板など平らなもので重しをし、冷めるまで放置しましょう。 ⑤冷めたらお好みサイズのひし形にカットし、下から緑・白・赤の順に重ねて完成です。 |
3.ひなあられ
菱餅と同様にカラフルで、春らしい色合いが雛祭りの雰囲気にぴったりなひなあられ。江戸時代頃には雛人形を屋外に持ち出して外の景色を見せてあげる「雛の国見せ」と呼ばれる風習があり、その際にひなあられを持参したとされています。
実はひなあられは「菱餅を砕いて作った」という説もあることから緑・白・赤(桃色)の3色のタイプが多く、それぞれの色の意味は菱餅と同じです。また、上記の3色に黄色が加わった4色のタイプも見られ、その場合は赤が春、緑が夏、黄色が秋、白が冬というように「四季」を表していると言われています。
ちなみに、ひなあられは関東と関西とで形や味付けが異なります。関東のタイプは米粒状で甘い味、関西では丸い粒状でしょうゆ味や塩味であるケースが一般的です。
用意する際はスーパーなどで購入する方が多いかもしれませんが、実はご自宅で簡単に手作りできます。菱餅を細かく切って揚げ、お好みの味付けをすれば完成なので、ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
※作り方の詳細は、ぜひレシピサイトなどでご確認ください。
4.桜餅
桜餅には特に由来や意味合いはないものの、雛祭りに取り入れられることが多い食べ物です。その理由には諸説ありますが、春らしいピンク×緑の配色が桃の節句にぴったりであること、さらには5月5日の子どもの日には「柏餅」を食べる習慣があることが影響しているとされています。
桜餅も関東と関西とで種類が異なり、関東では小麦粉で作った生地をふたつ折りにして餡をはさむ「長命寺(ちょうめいじ)」、関西では道明寺粉と呼ばれるもち米の生地で餡をくるむ「道明寺(どうみょうじ)」が主流です。関東風の桜餅は材料さえ準備できればご自宅でも作りやすいので、ぜひお子さまと一緒に手作りしてみてください。
※作り方の詳細は、ぜひレシピサイトなどでご確認ください。
5.ちらし寿司
おめでたい日のお料理として、雛祭りにも食べられることの多いちらし寿司。歴史的な背景などは特にありませんが、縁起の良い具材がお祝いの席にふさわしいこと、さらには色彩豊かで食卓が華やかになることなどから雛祭りメニューの定番となっています。
具材はお好みではあるものの、縁起物としては主に以下のものを取り入れるとよいでしょう。
・海老:長寿
・豆:まめになる
・れんこん:先行きを見通せるようになる(穴が開いているため)
ちなみにちらし寿司にはほかにもたくさんの具材を入れますが、その背景には「生涯食べ物に困らないように」という願いが込められていると言われています。ぜひお子さまが好きな具材なども取り入れながら、雛祭りらしい華やかなちらし寿司作りをお楽しみください。
|
●ちらし寿司のレシピ(2人分) 【材料】 【作り方】 ②れんこんの皮をむいて薄切りにし、酢水(水200ml+酢小さじ1/2)に5分程度漬けます。そして沸騰したお湯で3分程度ゆでたら、ざるに上げて水気をしっかりと切ります。 ③ボウルにれんこんと蒸しエビ(背ワタを取り水気を取り除いたもの)を入れ、甘酢70mlを加えて30分程度放置します。その後、れんこんの半分ほどをみじん切りにしておきましょう。 ④酢飯に椎茸とにんじんの煮物、さらにはみじん切りのれんこんを混ぜたものをお皿に乗せ、残りのれんこんやエビ、きぬさや、錦糸卵を飾り付けて完成です。 |
6. てまり寿司
ちらし寿司のほかに、てまり寿司も雛祭りに好まれやすいメニューです。ころんとした可愛らしい見た目が雛祭りにぴったりで、食卓を華やかに演出できます。
作り方はとても簡単で、お好みの具材と一口サイズの酢飯をラップに包んで丸めるのみ。お刺身はもちろんハムやチーズを乗せるなど、アレンジ自在でお楽しみいただけます。
7.はまぐりのお吸い物
ちらし寿司やてまり寿司に添える汁物としては、はまぐりのお吸い物がおすすめです。はまぐりは対の貝殻でなければぴったりと合わない特徴があることから、「良い結婚相手と結ばれますように」という願いを込めて多く取り入れられています。
作る際にははまぐりの砂抜きをしっかりと行うことがポイントで、水から昆布と一緒に火にかけることで貝のうまみを引き出します。弱火でじっくりと煮て、最後に少量の酒と塩でほんのり味付けをしましょう。
愛情たっぷりの雛祭りメニューで、特別感あふれるお祝いを
今回は雛祭りにおける代表的な食べ物を7つご紹介しましたが、行事食にこだわりすぎる必要はありません。あくまで「縁起物」や「雛祭りの雰囲気に合うもの」として参考にしながら、ご家庭のお好みで取り入れるとよいでしょう。
たとえば菱餅の代わりに3色のケーキを用意したり、ちらし寿司を洋風にアレンジしたりなど、主役であるお子さまの好みやご希望に合わせるのもおすすめです。ぜひお子さまの健やかな成長を願う気持ちを大切に、愛情たっぷりの雛祭りメニューを準備されてみてはいかがでしょうか。
\ お名前が入れられるアイテムで特別感アップ♡ /
1963年東京生まれ。祖父:原米洲(人間国宝)、母:原孝洲(女流人形師)。慶応義塾大学経済学部卒業後、大手出版社・集英社に入社。1987年父親の急逝により、家業である人形専門店に入社。1988年専務取締役就任。2008年に独立して株式会社ふらここを創業。女性活躍推進活動に注力し、2015年に経済産業省『ダイバーシティ経営企業100選』の認定を受ける。
スタッフ全員に光をあてたチーム体制を大切にし、人形業界全体の再興を見据え、「お客様に望まれる商品が多く作られるようになれば、業界も元気が出てくる。その先駆けになるものづくりを進める」ことをモットーとし、日本の美しい文化を次世代に伝えていくことをミッションとする。