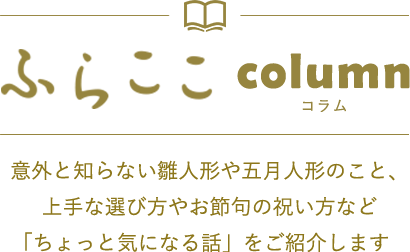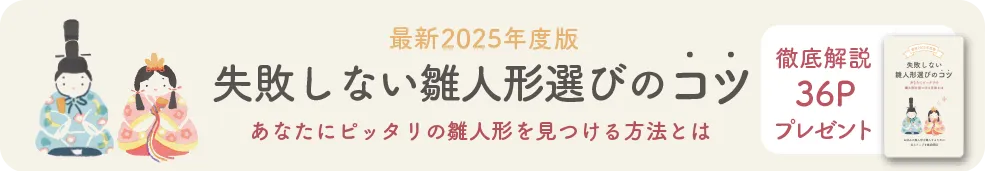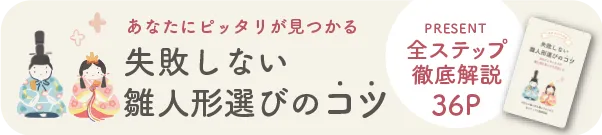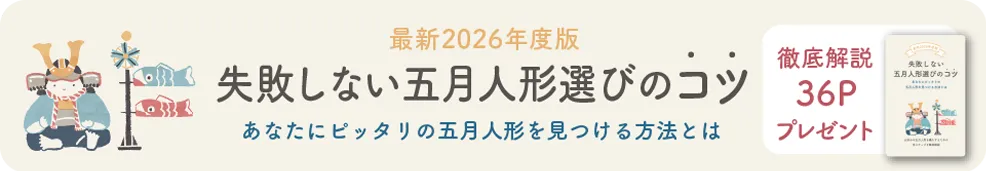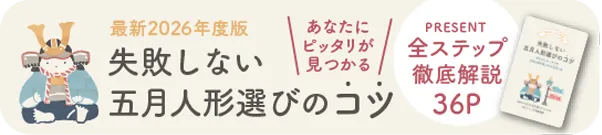わが子の健やかな成長と幸せを願って飾る雛人形。
せっかくお迎えしたお気に入りの雛人形だからこそ、お部屋に馴染む素敵な飾り付けをしたいですよね。
この記事では基本の飾り方から、おしゃれに飾るためのアイデアまで、わかりやすく解説いたします。
一年に一度の大切な日だからこそ、家族の記憶に残る素敵な一日にしましょう。
雛人形を飾る前に知っておきたい雛人形の基本
● 雛人形を飾る意味と由来
ひな祭りは、女の子の健やかな成長と幸せを願う日本の伝統行事ですが、その起源は中国から伝わった『上巳(じょうみ)の節句』という行事です。この行事が日本に伝わった当時は、身の穢れ(けがれ)や災いを「人形(ひとがた)」に移して水に流す祓い(はらい)の行事が中心でした。
また、平安時代に宮廷貴族の子どもたちは、“ひいな遊び”というままごと遊びを楽しんでいましたが、この“ひいな遊び”と、人形(ひとがた)を水に流す祓い(はらい)の行事が結びつき、長い時間をかけて今日のひな祭りになりました。
雛人形は、ただの飾りものではなく、子どもの健やかな成長を願ってていねいに飾ることが、今も昔も変わらず大切にされています。
● 飾る時期と片づける時期
・飾る時期の目安:節分の翌日になる「立春(2月4日前後)」〜「ひな祭り(3月3日)」の1週間前くらいまでに飾り終えておくのがよいと言われています。
地域によっては、二十四節気のひとつである「雨水(2月18日頃)」に飾ると、良縁に恵まれるという風習があるようです。
・片づけるタイミング:ひな祭り(3月3日)が終わったらなるべく早く、お人形が長持ちするよう、湿気の少ない晴れた日を選んで片づけましょう。
「雛人形をしまうのが遅れると、婚期が遅れる」という言い伝えがありますが、これは、子供たちに教育的なの意味合いで、後片付けの大切さを教えた言葉だったようです。
● 飾り方の種類と特徴
雛人形の飾り方にはさまざまなスタイルがあります。
・親王飾:女雛と男雛がペアになった雛人形。最もシンプルでコンパクトな飾り方です。
・五人飾:親王(女雛と男雛)に三人官女を加えた雛人形。親王飾より豪華に飾れて、飾るスペースも親王飾と同じくらいで済み、飾る手間もかからないため、とても人気がある飾り方です。
・段飾り:三段飾り、五段飾り、七段飾りがあり、親王(女雛と男雛)と三人官女のほかに、五人囃子や随身・仕丁、また雛道具などを組み合わせた、とても豪華な飾り方です。
・収納飾り:収納飾りは、飾り台と収納箱が一体になった雛人形。収納箱の中に人形や雛道具が全て収まり、1箱で保管ができるため、とても便利なスタイルです。
・ケース飾り:ケースに入った雛人形。ホコリからお人形を守れるので、飾っている期間のお手入れが簡単なのが嬉しいポイント。ペットがいるご家庭にも人気です。
● お人形の種類と特徴
雛人形は、作り方の違いで「木目込み人形」と「衣装着人形」の2種類に分けることができます。
・木目込み人形:古くから伝わる日本の伝統技術で、木製の胴体に筋を彫り、その溝に布を押し込む技法で衣装を着せた雛人形。造形を自由に作れるため、小さくて可愛らしく、コンパクトに飾れる雛人形です。
ことこと 琳派名物裂

商品名:ことこと 琳派名物裂/CT-01124400
サイズ:横幅42.5×奥行25×高さ25cm
価格:79,950(税込87,945円)
京都・西陣織で織り上げた、格調高い琳派名物裂のお衣装を着せ付けた雛人形です。伝統を大切にしながらも、優しく可愛らしいお人形は、ひな祭りを楽しい思い出にしてくれるでしょう。
ナチュラルな色合いの飾り台と、縁起の良い四つの草木をほどこした京刺繍のお屏風は、シンプルながら華やかさもあり、お部屋のインテリアと馴染みます。
https://www.furacoco.co.jp/hina/product/CT-01124400
・衣装着人形:仕立てた着物を人形の胴体に豪華に着せつけた雛人形。華やかに仕立てたお衣装を着せるため、見た目の豪華さが特徴です。
れいれい 衣装着・うめ東風

商品名:れいれい 衣装着・うめ東風/RE-05160000
サイズ:横幅40×奥行19×高さ25cm
価格:129,500(税込142,450円)
鮮やかな桃色のお化粧がよく映えるお顔だちの「れいれい」の衣装着雛人形です。慎ましくも華のある印象のれいれいにぴったりな、知性感じるフクロウ柄のお衣装は、正絹と金糸を使った滑らかな質感と、程よいツヤ感で高級感があります。裾や袖が均一に着重ねられた十二単(じゅうにひとえ)は名工人形作家・平安 芳峰(へいあん よしほう)が丹念に作り上げた技術ある上等な仕上りです。
https://www.furacoco.co.jp/hina/product/RE-05160000

【おしゃれ映え】雛人形の飾り方アイデア10選
現代では、特に都市部にお住いのご家庭は、和室がないご家庭が多くなっているため、リビングやダイニング、また玄関に雛人形を飾るご家庭が増えています。
そこで、現代の住まいに合わせたおしゃれな飾り方を10パターンご紹介いたします。
◎ スペース・空間を活かした飾り方
1.棚やニッチを活用した省スペース飾り
リビングのサイドボードやテレビ台の上などを使ったコンパクトな飾り方。近年では、玄関のニッチに雛人形を飾るご家庭も増えています。家族みんなで毎日見て楽しめる飾り方です。
2.壁飾りを使って立体感を演出
最近人気なのが、タペストリーやガーランドなどの壁飾りを使って立体感を演出する飾り方。まるでアートのように空間を彩れます。
◎ 小道具をプラスして
3.おしゃれな照明で雰囲気アップ
おしゃれな明かりを添えて雛人形をライトアップすると、立体感と温かみが増しておしゃれな雰囲気に。幻想的な雰囲気を演出するのも素敵ですね。
4.季節の花やグリーンと組み合わせる
桃の花や菜の花など、季節のお花やグリーンを飾ると、春らしさがアップ。自然の彩りでふんわり優しい印象になります。
5.おしゃれでモダンな敷物を使ってスタイリッシュに
伝統的な赤い毛氈(もうせん)ではなく、お部屋のトーンに合わせたモダンな敷物を使って、洗練された印象に。小さめのテーブルに敷物をかけて、そこに雛人形を飾っても素敵です。
◎ 人形の配置を工夫
6.親王飾だけをシンプルに飾る
親王飾なら、省スペースで飾れるだけでなく、飾り付けも簡単です。忙しいご家庭でも気軽にひな祭りを楽しめます。
7.あえて自由な配置で私らしい飾り方
伝統にとらわれすぎず、配置を変えたり、小物を足したりと自由に楽しむ飾り方も人気です。自分らしいアレンジで特別感を出してみてください。
◎ その他にも
8.色使いでセンスアップ
お部屋のインテリアに合わせた色合いの小物を揃えて、統一感を演出。おしゃれ度が一気に上がります。
9.ガラスケースを使わない開放的な飾り方
ケースに入れず、開放感のある飾り方にすると、写真映えも抜群。お人形の美しさが引き立つスタイルです。
10.夜も楽しめるライトアップ術
夕方から夜にかけて、雪洞(ぼんぼり)のやわらかな光で照らすことで、昼間とは違う雰囲気が楽しめます。ご家族の団らんのひとときにもぴったりです。
【これはNG!】雛人形の飾り方で避けたいこと
● 飾る場所の注意点
・直射日光・エアコンの風が当たる場所に飾らない
色あせや変形の原因になります。日が差し込む窓際やエアコンの風が直接当たる場所は避けましょう。
・湿気の多い場所には要注意
木製の素材は、湿気を吸収しやすいためカビやシミの原因に。窓際・水回り・結露しやすい壁面の近くは避け、風通しのよい場所に飾りましょう。
● 人形に触れるときは手袋や柔らかい布を使う
手の油分が人形に残ると、変色や劣化の原因になります。思わず触れたくなる雛人形だからこそ、取り扱いにも気を配りましょう。
● 片づけが遅れすぎないように
「片づけが遅れるとお嫁に行き遅れる」という言い伝えがありますが、湿気やカビによる人形の劣化を防ぐためにも、早めの片づけがおすすめです。3月中には片づけることを意識しましょう。
● 細かい付属品の収納に注意
飾り台や屏風、小道具などの小物は紛失しやすいので、専用の収納ケースや小袋でしっかりと整理しましょう。また、箱から出す前に写真を撮っておき、それぞれの小物のしまう場所が分からなくならないようにすると良いでしょう。
飾り終わった後の雛人形のお手入れと保管方法
● 基本のお手入れ
飾り終わったら、毛ばたきや布を使って、人形や雛道具についたホコリをやさしく取ってからしまいましょう。毛ばたきをお持ちでなければ、100均で売っている柔らかいメイクブラシで代用しても大丈夫です。強くこすらず、表面の汚れをやさしく払うのがポイントです。
● 湿気対策
桐箱や防湿ケースにしまうのが理想です。乾燥剤を入れて、湿気によるカビや劣化を防ぐことも忘れずに。
● 防虫対策
市販の防虫剤は、人形専用の無香タイプを選ぶと安心です。におい移りを防ぐことができます。また、乾燥剤と防虫剤は一緒に箱に入れても大丈夫です。
● 正しい収納方法
人形の顔に直接ものが当たらないよう、柔らかい紙や布でくるんでから収納しましょう。人形や雛道具を重ねないように注意し、パーツごとに整理して収納すると次回も飾りやすくなります。
まとめ
雛人形を飾る際に、決まりにとらわれすぎる必要はありません。
大切なのは、家族が笑顔になれる空間をつくること。昔ながらの伝統を大切にしながらも、ご家庭のインテリアやお好みに合わせて、ぜひ自由に飾り付けを楽しんでみてください。
その際に、先輩ママの飾り方を参考にして、自分なりにアレンジして飾ってみることをおすすめいたします。
ひな祭りが、あなたとご家族にとって特別な思い出となりますように。
1963年東京生まれ。祖父:原米洲(人間国宝)、母:原孝洲(女流人形師)。慶応義塾大学経済学部卒業後、大手出版社・集英社に入社。1987年父親の急逝により、家業である人形専門店に入社。1988年専務取締役就任。2008年に独立して株式会社ふらここを創業。女性活躍推進活動に注力し、2015年に経済産業省『ダイバーシティ経営企業100選』の認定を受ける。
スタッフ全員に光をあてたチーム体制を大切にし、人形業界全体の再興を見据え、「お客様に望まれる商品が多く作られるようになれば、業界も元気が出てくる。その先駆けになるものづくりを進める」ことをモットーとし、日本の美しい文化を次世代に伝えていくことをミッションとする。