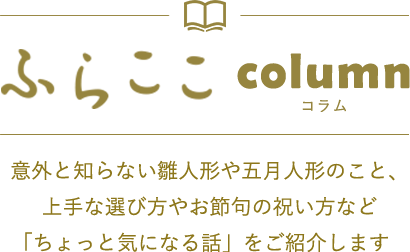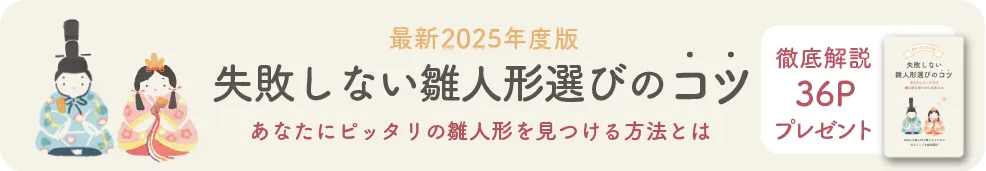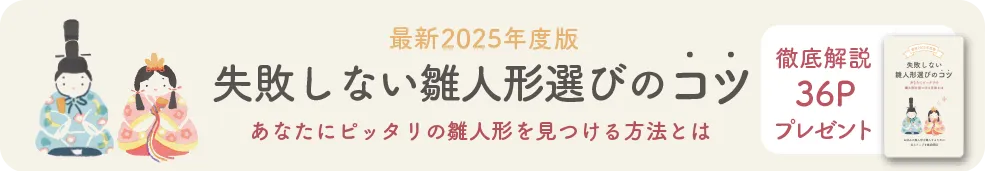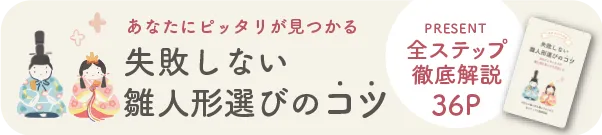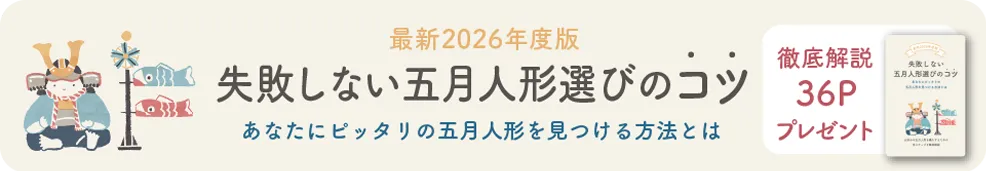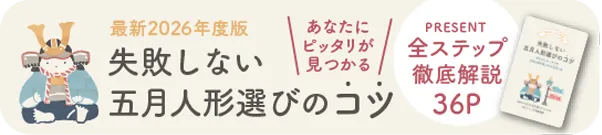お宮参りは、赤ちゃんやママにとって初めての外出を伴うイベントです。「神社で参拝する」という何となくのイメージはあるものの、「どこの神社がいい?」「初節句が先の場合はどうする?」「正装でないとダメ?」といった疑問や不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
そこで、今回はお宮参りに関する基礎知識を詳しくご紹介します。基本的なマナーをしっかりと押さえて、赤ちゃんやご家族にとって大切な「晴れの日」をスムーズに迎えましょう。
そもそも「お宮参り」とは?
お宮参りとは、赤ちゃんと一緒に神社を参拝する伝統的なお祝い行事です。赤ちゃんが無事に誕生したことのご報告を行うとともに、今後の健やかな成長を祈願します。
一般的には赤ちゃんが生まれた土地に根差した「産土神(うぶすながみ)」が祀られている神社に参拝しますが、もしも産土神社が複数ある場合はお好みのところを選ぶとよいでしょう。なお、「せっかくなら有名な神社に参拝したい」という場合は産土神社以外に出向いても構いませんが、赤ちゃんやママへの負担も考慮しながら慎重に検討することをおすすめします。
お宮参りにはいつ行くのがベスト?
お宮参りの時期は、「赤ちゃんが誕生してから1ヶ月前後」が目安です。具体的には男の子なら生後31日目~32日目、女の子なら生後32日目~33日目に行うのが正式なしきたりとされています。
とはいえ近年はそれほど厳密ではなく、必ずしも上記の日程で調整する必要はありません。赤ちゃんとママの体調や天候などを考慮し、ご家庭の都合に合ったスケジュールで行うとよいでしょう。
ちなみに「初節句」もお宮参りと同様に赤ちゃんの健やかな成長を願って祝う行事ですが、基本的には初節句よりもお宮参りのほうを先に行います。先述のように、お宮参りには「赤ちゃんの生誕を氏神様に報告する」意味合いもあるためです。
もしも1月~2月生まれの女の子、あるいは3月~4月生まれの男の子で初節句のほうが早く訪れる場合は、初節句を翌年にずらしても問題ありません。ただし、地域やご家庭によってはお宮参りと初節句を同じタイミングで行うケースもあるため、迷う場合は赤ちゃんの祖父母に相談して決めると安心です。
また、お宮参りの日取りを決める際に大安や仏滅といった「六曜(ろくよう)」を気にされる方もいることでしょう。お宮参りのような記念行事ではそれほど気にする必要はありませんが、可能であれば縁起が良いとされる以下の日取りを選ぶことをおすすめします。
|
・大安 ・先勝 ・友引 |
お宮参りの服装は?
お宮参りを迎えるにあたり、服装をどうしようか迷う場合もあるのではないでしょうか。ここでは赤ちゃんとご家族それぞれに適した服装について解説します。
・赤ちゃんの服装
お宮参りにおける赤ちゃんの正装は、純白の絹生地で作られた「白羽二重(しろはぶたえ)」と呼ばれる内着の上に祝着(のしめ)を羽織るスタイルです。のしめは男の子と女の子とで以下のように模様や色合いが異なります。
|
【男の子の場合】 【女の子の場合】 |
なお、お宮参りの服装に厳密なルールはないため、無理に正装をさせる必要はありません。「ベビードレス×ケープ」の洋装スタイルや普段よりも少しよそ行きの服装など、ご家庭のお好みで決めるとよいでしょう。
・ご家族の服装
ご家族の服装は、フォーマルであれば問題ありません。なかには紋付や着物を着るママも見られますが、近年ではスーツやワンピース、セットアップなどを選ぶケースが多い印象です。
赤ちゃんの服装と同様に厳格なルールはありませんが、カジュアルなタイプや派手な雰囲気のものは避けるほうがよいでしょう。お宮参りという大切なお祝い行事であることを意識して、控え目なスタイルを選ぶことをおすすめします。
迷われる方はスーツの専門店にご相談されると良いでしょう。
「オーダースーツSADA」では最短2週間でスーツをフルオーダーすることもできます。
お宮参りに関する3つのマナーをチェック
最後に、お宮参りを迎えるにあたって押さえておきたいマナーを3つご紹介します。
(お宮参りのマナーその1)初穂料について
ご祈祷を神社にお願いする場合は、お布施として「初穂料」を納めます。神社によっては金額が決まっている場合もありますが、相場としては5,000円~10,000円程度を包むケースが一般的です。
お札は新札またはできるだけ綺麗なものを用意し、紅白で蝶結びになった水引がついているのし袋に入れて持参しましょう。ただし、神社によってはのし袋に入れずに直接受付に納めるところもあるため、事前に確認しておくことをおすすめします。
(お宮参りのマナーその2)赤ちゃんを抱く人について
古くからの風習においては、お宮参りでは「父方の祖母」が赤ちゃんを抱くことが望ましいとされています。昔は「出産=穢れ(けがれ)」と考えられており、穢れの残った産後間もないママではなく別の女性(昔の女性は結婚したら嫁ぐケースが多かったため、近くにいる父方の祖母)が抱くしきたりが根付いていました。
しかし、現代のお宮参りでは昔のようなルールはなく、基本的には誰が抱いても問題ありません。とはいえ地域やご家庭によっては気にする場合もあるので、誰が抱くのかを事前に話し合っておくとよいでしょう。
(お宮参りのマナーその3)参拝の仕方について
神社における参拝のお作法についても、あらかじめ確認しておけると安心です。神社は以下のように「二礼二拍手一礼」で参拝します。
| 1.神前で深いお辞儀を2回行い、胸の高さで2回拍手します 2.手をきちんと合わせ、感謝の気持ちを込めながらお祈りをします 3.最後にもう一度深いお辞儀をします |
もしもお寺でお宮参りを行う場合には、合掌しながら一礼してお祈りをするスタイルで参拝しましょう。神社のように拍手はしないため、間違えないように注意が必要です。
ご家庭らしいスタイルでお宮参りを迎えましょう
日本古来のお祝い行事であるお宮参りには、時期や服装、赤ちゃんを抱く人などさまざまな風習があります。しかし、「赤ちゃんの誕生を祝いながら今後の健やかな成長をお祈りすること」が本来の目的なので、しきたりにこだわりすぎず、赤ちゃんやご家族の都合に合ったスタイルで行うとよいでしょう。
無理のないスケジュールや余裕を持った準備で、ぜひ素敵なお宮参りをお迎えください。
1963年東京生まれ。祖父:原米洲(人間国宝)、母:原孝洲(女流人形師)。慶応義塾大学経済学部卒業後、大手出版社・集英社に入社。1987年父親の急逝により、家業である人形専門店に入社。1988年専務取締役就任。2008年に独立して株式会社ふらここを創業。女性活躍推進活動に注力し、2015年に経済産業省『ダイバーシティ経営企業100選』の認定を受ける。
スタッフ全員に光をあてたチーム体制を大切にし、人形業界全体の再興を見据え、「お客様に望まれる商品が多く作られるようになれば、業界も元気が出てくる。その先駆けになるものづくりを進める」ことをモットーとし、日本の美しい文化を次世代に伝えていくことをミッションとする。