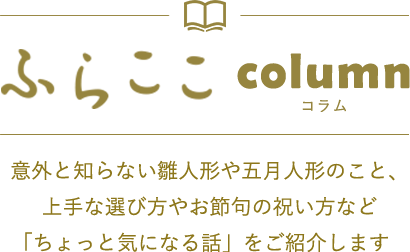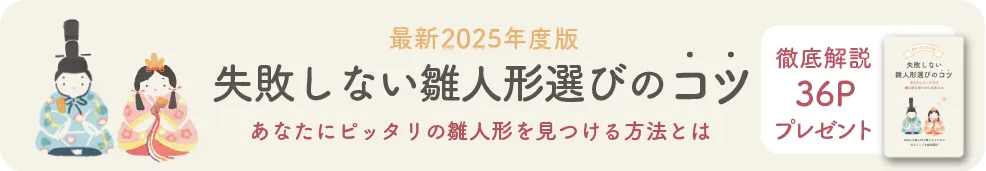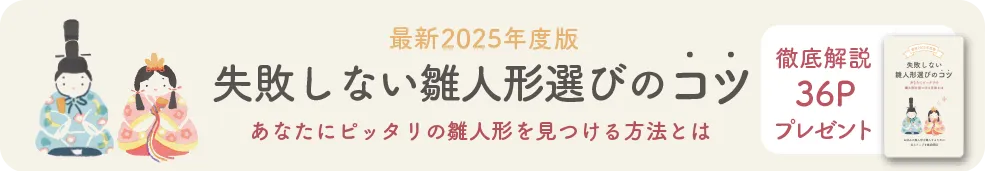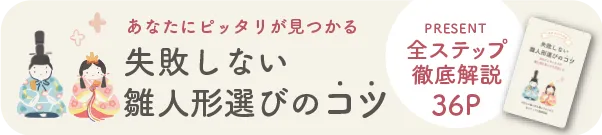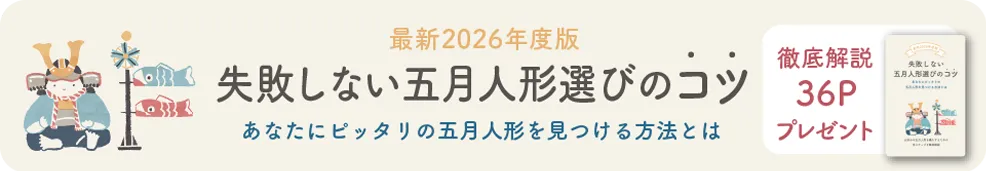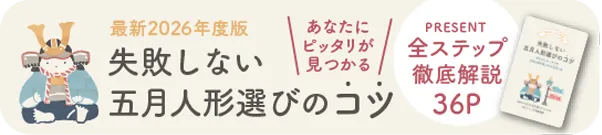男の子の赤ちゃんが生まれて初めて迎えるお正月には、「破魔弓(はまゆみ)」を贈る風習があります。厄払いの意味を持つ縁起物ですが、「誰が買うのか」「飾る時期やしまう時期はいつ?」などと気になっている方もいるかもしれません。
そこで、今回は破魔弓の意味や由来といった基礎知識をご紹介しながら、「誰が買うものなのか」に決まりはあるのかを解説いたします。また、合わせてチェックしておきたい「飾り方やしまい方」についても詳しくまとめました。
赤ちゃんに破魔弓を贈ることを検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。
\ 赤ちゃんが生まれたら必見! /
「破魔弓」の意味や由来について
まずは、破魔弓の意味や由来について知識を深めておきましょう。
破魔弓とは弓の形をした置物で、男の子の初正月の際に「わが子を邪気から守ってくれますように」という願いを込めて飾られることの多いお祝い品です。破魔弓は「魔を破る弓」と表記しますが、昔は弓矢で射る的のことを「ハマ」と呼んでおり、そこに「邪気を払う」という意味を込めて「破魔」という漢字をあてたことが由来とされています。
破魔弓の歴史は古く、大和時代(西暦647年頃)に宮中で行われていた正月行事である射礼(しゃらい:弓で的を射る儀式)が起源だと考えられています。当時、弓は「邪気を払う力を持つ神聖なもの」と信じられていたことから、宮中におけるさまざまな行事に用いられていました。
現代のように「魔除けのお守り」として飾られるようになったのは鎌倉時代頃で、武士にとって大切な弓矢を男の子の初正月に贈る風習が生まれたことがきっかけです。その風習は次第に民間にも伝わり、いつしか「男の子の初正月に自宅に飾る縁起物」として広く取り入れられるようになりました。
ちなみに破魔弓は「破魔矢(はまや)」と一緒に飾られることが多く、そもそも破魔矢のほうが一般的によく見かけるかもしれません。初詣の際にはお寺や神社などで授与されており、男の子がいる・いないにかかわらず「魔除け」として飾るご家庭が多くみられます。
破魔弓を「誰が買うのか」に決まりはある?
破魔弓には「誰が買う」という厳密なルールはありません。しかし、古くからの風習では母方の実家が用意するケースが一般的でした。
昔は結婚すると男性側の家庭に入る女性が多く、女性側の両親は娘や孫に会いづらくなる傾向があったとされています。そのため、祝い事のたびにお祝い品を持参し、娘や孫に会いに行ったものでした。
現代は核家族化が加速しており、父方の実家に対する関係性と母方の実家に対する関係性はほとんど変わりません。破魔弓をはじめとするお祝い品に対しても「誰が用意してもよい」と考えるご家庭が多く、両家で折半する場合もあれば父方の実家が購入するケースもあるなどさまざまです。
ただし、なかには昔からのしきたりを気にするご家庭もあるので、誰が買うのかはよく相談し合って決めるとよいでしょう。
破魔弓の「飾り方」と「しまい方」をチェック
破魔弓は基本的にお正月に飾るものですが、「いつから飾っていつ頃しまうのか」「飾る場所や収納の仕方はどうする?」などと迷うご家庭もあることでしょう。そこで、ここでは破魔弓の飾り方としまい方について詳しく解説いたします。
・破魔弓の飾り方
破魔弓を飾るタイミングとしては、「12月中旬の大安の日」が良いとされています。破魔弓は門松やしめ縄などと同じ正月飾りなので、「正月事始め」と言われる12月13日を目安に準備するとよいでしょう。
近年ではクリスマスを過ぎてから用意するご家庭も多いですが、「二重苦(にじゅうく)」や「一夜飾り」として縁起が悪いと言われる29日・31日に飾ることは避けることをおすすめします。
なお、破魔弓はかつて格式高い床の間に飾られていましたが、現在は床の間がない住宅も多く、飾る場所に厳密な決まりはありません。縁起物なので家族が集まるリビングに設置したり、「わが子を見守ってくれますように」という意味合いでお子さまの寝室に飾ったりと、各ご家庭のスタイルに合わせて取り入れてみてください。
・破魔弓のしまい方
破魔弓をしまうタイミングとしては、「小正月(1月15日)を過ぎた頃」が一般的です。とはいえ縁起物なので、一年中飾っていても問題ありません。
もしも年中飾りにしない場合は、「晴れて乾燥した日」を選んで収納します。破魔弓のような飾り物は湿気に弱く、雨の日や湿気の多い日にしまうと保管中にカビが発生しやすくなるため注意しましょう。
片付ける際には付着しているホコリを取り除き、除湿剤や防虫剤とともに箱の中に入れて収納します。せっかくのお祝い品なので、長く綺麗に飾れるように慎重にケアすることが大切です。
ご家庭に合ったスタイルで破魔弓を取り入れましょう
破魔弓は「邪気を払う魔除け」として男の子の初正月に飾る風習があり、昔ながらの用意の仕方や飾り方が存在します。
とはいえお子さまの健やかな成長を願って飾る気持ちが大切なので、古くからのしきたりにこだわりすぎる必要はありません。ご両家それぞれのお気持ちや飾る場所・収納場所のご事情などを考慮しながら、ご家庭に合ったスタイルで取り入れてみてください。
大切なお子さまの初節句にぴったり!ふらここのおしゃれな五月人形はこちら>
\ 初正月が終わったら初節句!五月人形の出番です🥰 /
1963年東京生まれ。祖父:原米洲(人間国宝)、母:原孝洲(女流人形師)。慶応義塾大学経済学部卒業後、大手出版社・集英社に入社。1987年父親の急逝により、家業である人形専門店に入社。1988年専務取締役就任。2008年に独立して株式会社ふらここを創業。女性活躍推進活動に注力し、2015年に経済産業省『ダイバーシティ経営企業100選』の認定を受ける。
スタッフ全員に光をあてたチーム体制を大切にし、人形業界全体の再興を見据え、「お客様に望まれる商品が多く作られるようになれば、業界も元気が出てくる。その先駆けになるものづくりを進める」ことをモットーとし、日本の美しい文化を次世代に伝えていくことをミッションとする。