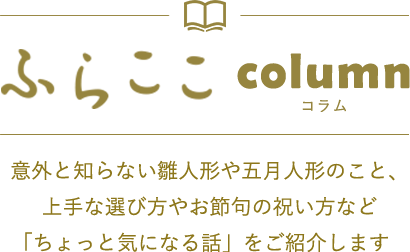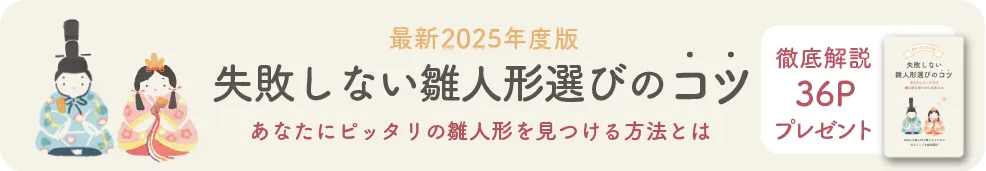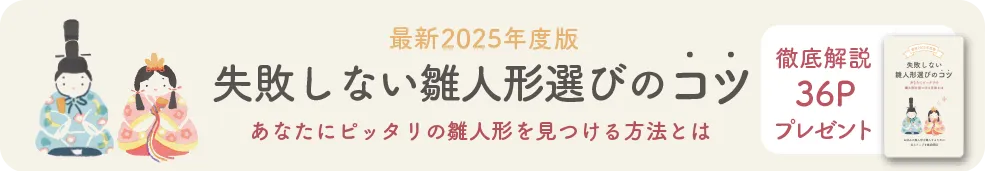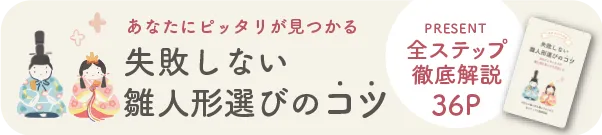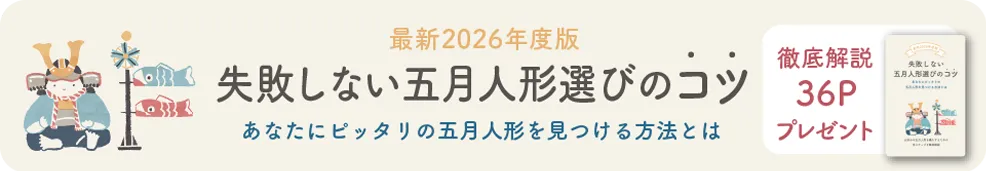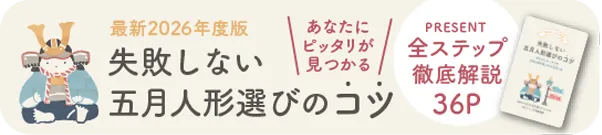5月5日の「端午の節句」のお祝いとして飾られることの多い、兜飾や鎧飾、大将飾といった五月人形。日本の文化として古くから大切にされている伝統行事ですが、「いつからどんな意味合いで五月人形を飾るようになったのか」「そもそも端午の節句とは何か」など、五月人形の歴史や由来をご存知の方は少ないかもしれません。
そこで、今回は「五月人形の歴史」に焦点を当て、端午の節句の際に飾る理由やスタイルの移り変わりについてまとめました。また、現代における五月人形のトレンドにも触れながら、ふらここで人気の商品3選もご紹介いたします。
五月人形を飾る由来とスタイルの移り変わり
端午の節句の起源は古く、奈良時代までさかのぼります。現代のように芸術品や嗜好品として五月人形を飾るようになったのは江戸時代頃といわれており、時代が移り変わるなかで行事の意味合いやスタイル、飾る物などが少しずつ変化していきました。
ここでは端午の節句における奈良時代~現代までの歴史に注目し、どのような経緯で、そしてどのような意味合いで五月人形が飾られるようになったのかを探っていきましょう。
・奈良時代~鎌倉時代
端午の節句は、奈良時代に古代中国から日本に伝わった「厄払い」の風習が起源とされています。中国では奇数を重ねた日である「五節句」の時期に邪気が近づきやすいと考えられており、五節句のひとつである5月最初の午(うま)の日には邪気を払う行事が行われていました。
その風習が日本に伝わるなかで、もともと日本で行われていた厄払いの儀式と融合して定着していったと言われています。ちなみに午(うま)は午(ご)とも読み、5に通じることから、次第に5月5日が「端午の節句」として固定されていきました。
端午の節句は初めから広く浸透していたわけではなく、平安時代頃までは宮中を中心に行われた行事だったと伝えられています。この日に宮廷では菖蒲(しょうぶ)やよもぎの葉を軒先につるしたり、臣下の人々は菖蒲を冠に飾ったりといったスタイルで厄除けをしていました。
しかし、その後徐々に貴族は衰退していき、時代は武家中心の鎌倉時代へ。端午の節句の代名詞であった菖蒲を「尚武(しょうぶ:武道や武勇を重んじること)」と解釈するようになり、さらには「勝負」にも通じることから、端午の節句は武家が中心のお祝い行事へと変化していきます。
この頃から菖蒲の葉を用いた厄払いの風習に加えて、男の子に甲冑や兜、太刀といった武具を贈るようになりました。また、民間でも軒先に菖蒲の葉を飾ったり、子どもたちが菖蒲の葉を刀に見立てて遊んだりと、菖蒲に関する風習が盛んになっていったと言われています。
・江戸時代
江戸時代になると、端午の節句は幕府において重要な式典が行われる日として重んじられるようになりました。大名や旗本が武将姿で江戸城に参内し、将軍にお祝いの品物を贈呈したとされています。
また、将軍の家に男の子が生まれると、城内に幟(のぼり)や模造の兜や鎧、槍(やり)、薙刀(なぎなた)などを立てて盛大に祝う風習が根付いていきます。民間でもこれを真似て、紙で作った大きな鎧兜や人形などを人目に付きやすい屋外に飾るようになりました。
このように端午の節句は武家のみならず民間にも浸透し、次第に「男の子の誕生を祝い、成長を願う日」といった意味合いが強まっていきます。そして、模造の兜や鎧はいつしか屋外ではなく屋内に飾るようになり、現代のように芸術品・嗜好品として「五月人形」を楽しむスタイルが定着していきました。
・明治時代以降~現代
明治時代に入ると、端午の節句は一時的に衰退します。新政府の方針によって「五節句の廃止」が打ち出され、新たに国の祝祭日が定められたためです。
しかし、端午の節句はすでに人々の暮らしのなかに深く根付いていたことから復活を遂げ、今日まで大切に受け継がれています。
現代の五月人形は「コンパクト」がトレンド!ふらここのおすすめ商品もチェック
かつては大きなサイズの五月人形が主流で、床の間などに盛大に飾られたものでした。しかし、近年は核家族化に伴ってコンパクトな間取りのマンションに住むご家庭が多く、そういった住宅事情にマッチする省スペースな五月人形が人気を集めています。
ふらここの五月人形は場所を取らないコンパクトサイズで、お人形が中心の「大将飾」・兜がメインの「兜飾」・迫力ある鎧をコンパクトに仕上げた「鎧飾」の3種類をバリエーション豊富にご用意しております。ここでは特に人気の商品を3点ピックアップしたので、ぜひ気軽に設置しやすいサイズ感や繊細なつくり、今風のお部屋に馴染みやすいデザインなどに注目しながらご覧ください。
【大将飾】
・勇(ケース入り)
商品名:勇(ケース入り)/ T-000021500
サイズ:横幅32cm×奥行24cm×高さ25cm
価 格:90,500円(税込99,550円)
~商品の特徴~
大きな瞳の可愛らしいお人形をメインに、迫力ある兜や刀で力強さも表現した大将飾です。刀は江戸時代後期頃に端午の節句の観賞品として親しまれた「菖蒲太刀(しょうぶだち)」で、脇に添えた花飾りとともに「菖蒲のように丈夫な子に育ちますように」という願いを込めました。
ガラスケース入りなのでお人形や花飾りにホコリが付着しにくく、お手入れがしやすい点もうれしいポイントです。
https://www.furacoco.co.jp/gogatsu/product/T-000021500
【兜飾】
・透彫飛鷹鍬形の兜(すかしぼりひようくわがたのかぶと) / 収納タイプ
商品名:透彫飛鷹鍬形の兜(収納タイプ) /K-000111500
サイズ:横幅39cm×奥行29cm×高さ45cm
価 格:99,800円(税込109,780円)
~商品の特徴~
繊細なつくりの兜と弓太刀がセットになった、落ち着いた雰囲気の兜飾です。兜の鍬形(くわがた)には純金鍍金(じゅんきんめっき)で仕上げた鷹の透かし彫りを、吹き返し部分には鷹が翼を広げる様子を彫金であしらい、「わが子が力強く成長しますように」と願う親御様の想いを表現いたしました。
黒を基調としたシックな配色や風情あるデザインが魅力で、コンパクトながらも存在感は抜群です。
https://www.furacoco.co.jp/gogatsu/product/K-000111500
【鎧飾】
・縹裾濃糸縅の鎧(はなだすそごいとおどしのよろい)
商品名:縹裾濃糸縅の鎧(Y-000330300)
サイズ:横幅30cm×奥行29cm×高さ31cm
価 格:108,500円(税込119,350円)
~商品の特徴~
本格的なつくりの兜や鎧をコンパクトサイズに仕立てた、何ともおしゃれな鎧飾です。鍬形には純金鍍金をあしらい、縅糸(おどしいと)には正絹、吹き返しや胴には鹿の皮を使用するなど素材にもこだわった逸品で、邪気を払う魔よけの意味合いを込めて太刀と菖蒲飾りも添えました。
ナチュラルな飾り台やお屏風はあらゆるインテリアに馴染みやすく、美しい配色のため空間のほどよいアクセントにもなるでしょう。
https://www.furacoco.co.jp/gogatsu/product/Y-000330300
伝統を大切に、年に一度の節句行事を楽しみましょう
長い歴史のなかで、少しずつ形を変えながら親しまれてきた端午の節句。行事の由来や五月人形を飾るようになった経緯に注目することで、節句行事をより身近に感じ、より深くお楽しみいただけるでしょう。
ふらここでは古き良き伝統を大切にしつつ、現代のニーズにマッチした五月人形を種類豊富に取り揃えております。見るたびにうっとりするようなおしゃれな商品が充実しているので、これから初節句を迎える方はぜひ以下のラインナップをチェックしてみてださい。
1963年東京生まれ。祖父:原米洲(人間国宝)、母:原孝洲(女流人形師)。慶応義塾大学経済学部卒業後、大手出版社・集英社に入社。1987年父親の急逝により、家業である人形専門店に入社。1988年専務取締役就任。2008年に独立して株式会社ふらここを創業。女性活躍推進活動に注力し、2015年に経済産業省『ダイバーシティ経営企業100選』の認定を受ける。
スタッフ全員に光をあてたチーム体制を大切にし、人形業界全体の再興を見据え、「お客様に望まれる商品が多く作られるようになれば、業界も元気が出てくる。その先駆けになるものづくりを進める」ことをモットーとし、日本の美しい文化を次世代に伝えていくことをミッションとする。